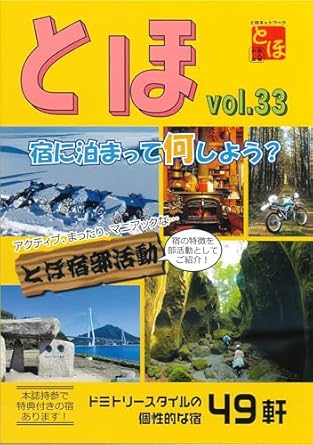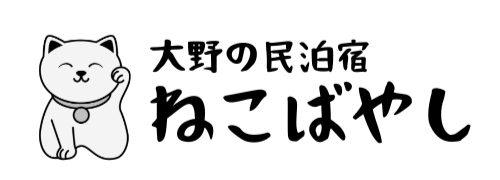「とほ宿誕生」 北国通信 小鹿信平
旅人宿の第1時期は「船長の家」などの数件。それらの宿やY.H(ユースホステル)でヘルパーをした旅人が旅の最終目標にしたのが自分の手で宿を造ることで、1980年前後(第2時期)北海道内いたる所で旅人宿が誕生しました。それらの宿をはじめて紹介したのがゲラ刷りで書かれた「ユニーク民宿表」(旧すっから館発行)簡単なコメントが記載されてる住所録で、この「ユニーク民宿表」が宿々でコピーされ旅人へと広がっていき反響の大きさが「とほ」の誕生になったのです。
旅人宿は独創かつ自由奔放、しかるに質素と貧乏がトレードマーク、一般の民宿との違いは一目瞭然でした。廃屋のリサイクルであっちこっちに宿が生まれたのです。小さな宿と言っても一国一城のあるじである宿主は絶対の権限を持ち個性的な独自の宿を展開し発展させます。皆宿に誇りを持ってましたから「ボロは着てても心は錦」、情報誌に宿を紹介すると自分の宿が求めるのと違う旅人が来るから邪道であり、唯一口コミが最良の伝達方法で、それ以外は拒否すると宣言する宿主もあり「とほ」の船出は多難でした。
当時北海道へは多くの旅人が来てましたが、そのほとんどが有名Y.Hや限られた人気の宿へ集まる。「とほ」の宿では知り合いの宿同士で客を回し合ったり、客にチラシを持たし人気の宿で宣伝したり。さながらゲリラ戦術で、ブラブラしている旅人を見つけたら「今日泊まる宿決まってる?」と声を掛け「待っていても客は来ない、客の所に行って連れてくる!」のが常識でした。また旅行情報誌も極端に少なかったです。唯一北海道を旅する人たちが中心となり旅人サイドから見た北海道を書いた「とらべるまんの北海道」が旅人に愛読されていました。表紙には、次のような注意書きが記されている「この本は、とらべるまん独自の体験と実地調査をもとに道楽で書き上げたものです。そのため独断と偏見に満ちており、まれにアレルギー反応や中毒症状を起こす恐れがありますが、当方はいっさい関知致しません。」
そして、数年後、海を渡って大群のミツバチ続が旅人宿に押し掛けてきたのです。ミツバチ族来襲!宿を救うのは旅人!この時旅人宿の存在がようやく世に知られました。
そしてマスメデマ(原文ママ)が北海道観光に火をつけます。富良野のラベンダー畑を一躍有名にした「アンアン」、テレビ番組では「北の国から」。旅行情報誌が北海道旅行をアレンジし始めます。「とらべるまんの時代」は終わり「アンノン族とミツバチ族の時代」へ。「とほ」の宿も30件から60件、第3時期へ突入していきます。旅人宿と言う愛称も定着し宿の方向は独創的指向より安定型指向へ、廃屋は姿を消し新築が目立ち始め、旅人宿イコール貧乏や汚いということばも聞かれなくなり、また旅人の変化も宿に影響をあたえ始めました。
さて「アンノン族とミツバチ族の時代」の次にはどのような時代が来るのでしょうか?時代はまた、旅人宿が誕生した時のような独創的な宿を求め始めているのかもしれません。そして情報も、旅人が宿に発信する時代になるのではないでしょうか。「ボーイズ ビー バックパッカーズ」「青年よ旅に出よ!」私たち「とほネットワーク」は「バックパッカーの時代」が来ることを望みます。
旅の情報誌「なまら蝦夷」創刊号(1996年4月刊行)P58より
==
「とほネットワーク旅人宿の会」のホームページはこちら